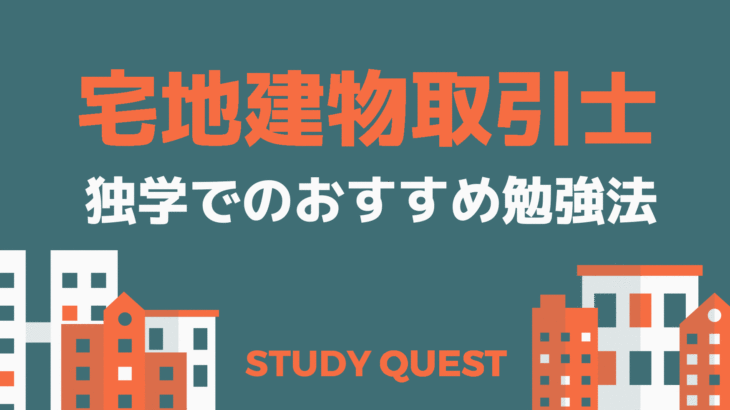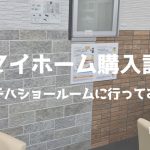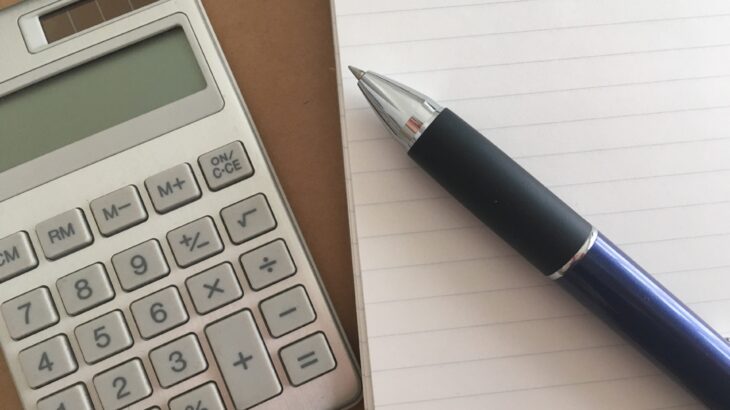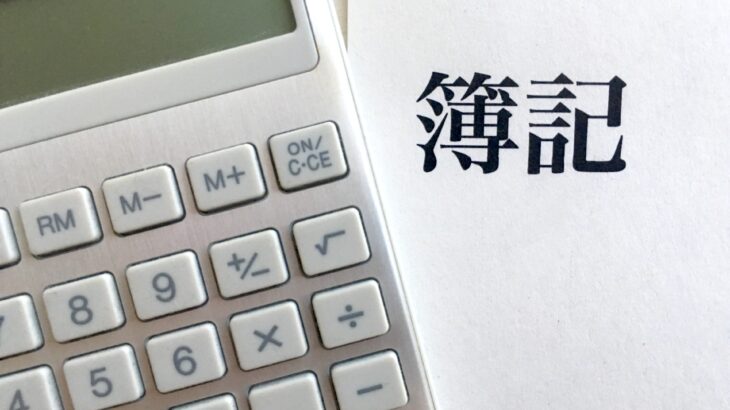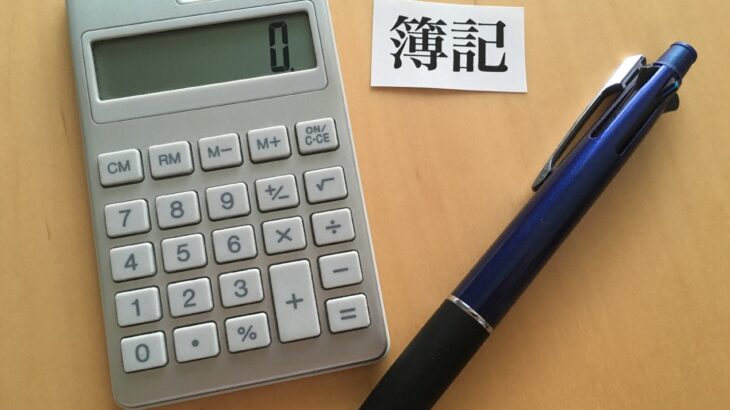このブログでは、いろいろな資格取得に挑戦して、独学勉強のコツやおすすめのテキストなどを紹介しています。
今回は宅建に挑戦しました!正確に言うと『宅地建物取引士』ですね。略して『宅建』。
「就活で不動産業界を目指してて、在学中にとれれば…」という大学生や、「宅建取って転職に活かせれば…」という社会人の人も多いと思います。
今回、この宅建試験に完全独学で挑戦してみました。
この記事を読んでもらえれば、「そもそも宅建試験って合格するの難しいの?」「独学で受かる?スクールに通った方がいい?」「教材は何を選べば…?」というみなさんの疑問も解消できると思います。
そもそも『宅建』って独学で合格できる?
なんと言ってもみなさんが知りたいのはコレですよね。
結論から言うと、宅建試験には独学でも十分合格できます。
ただ、どんな人でもどんなやり方でも独学で合格できるわけではないですし、最低限必要な勉強時間もあります。
今回はそのあたりの「独学での宅建合格に必要なこと」を、僕の経験も交えながら書いていきますね。
独学での宅建合格に必要なこと
宅建試験に限らずなんですが、資格の勉強をする上で大切(というか必須!!)だと思うのが次の4つです。
これを自分ひとりでできる人はどんな勉強でも独学でクリアできるでしょう。
① 試験を知ること
② 正しい道具を選ぶこと
③ 適切な計画を立てること
④ 計画通り着実に進むこと
この4つを「全部自分ひとりでこなせそう!」という人は独学でも大丈夫。もちろん完全に独力で、という意味ではなく「ネットで調べたり詳しそうな人を見つけてわからないことを自分から質問したり、というのが自分からできる」という意味です。
逆に「これを全部自分でやるのは面倒だな…、いや面倒というかできる気がしない…、てかそもそも自分で決めたことが続いたことない…」という人は資格スクールに通った方がいいかもしれません。
資格スクールはお金はかかりますがその分、この4つをしっかりやってくれるので、一人ではできないという人も安心ですね。
それから、「独学での宅建合格に必要な勉強時間は?」と気になる人もいますよね?
上記の「①試験を知ること」「③適切な計画を立てる」のところで必ず検討しないといけない勉強時間のこともお伝えしていきますね。
「宅建の勉強、独学で挑戦してみようかなー」とちょっとでも思える人は読み進めてください!
宅地建物取引士(宅建)試験について
独学で勉強を始めるときは、いきなりテキストを買って読み始めたらダメです。
まずは、宅建試験がどんな試験なのかを正しく知る必要があります。試験の形式や配点、試験日や年間の試験回数などで、どんなテキストや問題集を選べばいいか、どういう勉強スケジュールを立てればいいかがまるっきり変わってくるからです。
最初にやるべきは敵を正しく知ることです!
宅建試験の基本情報
出題形式
◆出題形式:四肢択一
◆回答形式:マークシート
◆出題数:50問
◆試験時間:2時間
※5点免除者は45問・1時間50分
出題内容
宅建試験の出題内容は大きく分けると4つの科目と5点免除科目となります。
出題科目と、それぞれの科目からの出題数は次のようになっています。
◆宅建業法:20問
◆権利関係(民法、借地借家法、不動産登記法など):14問
◆法令上の制限(都市計画法、建築基準法など):8問
◆税・価格など(不動産検定評価・地価公示、税法など):3問
◆5点免除科目(景品表示法、統計、土地建物の知識など):5問
合格点・合格率
宅建試験の合格点は、その年によって違います。
ここ10年でいうと、31~36点の間で、平均33.7点となっています。
合格率はだいたい15〜18%くらいの間ですね。
この宅建試験の勉強のイメージは、
●宅建業法を確実にする
⇓
●その他の科目はまずはテキストを広く浅く
⇓
●一問一答型の問題集で科目内の項目を1つずつ潰していく
⇓
●過去問題集を解いて雰囲気になれる
⇓
●予想問題集で本番に備える
という感じです。
宅建業法が一番とっつきやすいので、早い段階で攻略できると漠然とした不安感が多少は払拭できるかなと思います。
目標は、試験直前期に38点とれるようになってることです!
宅建合格におすすめのテキスト・問題集
ここまで読んでもらうと、「じゃあ何を使って勉強すればいいの?」となると思います。
僕が宅建の独学勉強する中でいろいろ調べて吟味した結果、こちらがおすすめのテキスト・問題集です。
おすすめテキスト
② みんなが欲しかった!宅建士の教科書(楽天で見る・Amazonで見る
)
おすすめ問題集
③ みんなが欲しかった!宅建士の問題集(楽天で見る・Amazonで見る
)
④ みんなが欲しかった!宅建士の12年過去問題集(楽天で見る・Amazonで見る
)
おすすめ予想問題集
⑤ 本番試験をあてる TAC直前予想 宅建士(楽天で見る・Amazonで見る
)
⑥ みんながほしかった!宅建士の直前予想問題集(楽天で見る・Amazonで見る
)
⑦ LEC 出る順宅建士 直前大予想模試(楽天で見る・Amazonで見る
)
おすすめアプリ
おすすめテキスト(番外編)
宅建合格までの勉強スケジュール
次に、上で紹介したおすすめ教材のどれを使って、どういう順番で、どれくらいの時間勉強したらいいのかを僕の経験でお話しします。
あくまで僕が考えるちょうどよいスケジュールなので、勉強が心配な人や試験日まで日数がある人はもっと時間をかけてもいいです。
逆に、勉強には自信があるという人や、試験日まで日にちが全然ないという人はスケジュールをもっと短く圧縮してもいいかもしれません。
そこを踏まえてのおすすめの勉強スケジュールは、
0.とりあえず過去問にチャレンジ(1日)
1.テキストをざっくり読む(2週間)
2.テキスト2週目+項目ごとに問題集を解く(1ヶ月間)
3.過去問+苦手な項目を復習する(1ヶ月間)
4.予想模試で腕試し(2週間)
(※期間は目安です。勉強の頻度や一日の勉強時間によって期間は変わってきますね)
です。
以下、0〜4を詳しく説明していきます。
0.とりあえず過去問にチャレンジ
まずはテキストで勉強する前に、一度過去問を解きましょう。
「え?いきなり過去問??」と思うと思いますが、いきなり過去問です笑。基本的にはどんな勉強でもまず過去問をやってみた方がいいです。
理由は「何がわからないのか」「どれくらい難しいのか」を体感できるからです。まずは自分の現在地を知ることが大事なんですね。
はじめに過去問を解くと「全く勉強していない今の状態でも○点は取れる」とか「四択と思って舐めてたけど一つ一つの選択肢をきちんと判断しないと正解選べないな」とか「うお!時間全然足りないな…」とかが体感的にわかります。
過去問を解くことで何かしらの気づきを得ておくと、その後の勉強でどこに重点を置いた方がいいかがわかりやすいです。
1.テキストをざっくり読む
ここからが本格的な勉強です。テキストを読み進めていきましょう!
おそらく最初は、書いてある内容の意味が全然わからないと思いますが、ひとまずこの期間ではわからないことは読み飛ばしてOKです。ここで時間をかけて最初からテキストの内容をくまなく覚えようとする必要はありません。
この後にテキスト2周目に入るのでそのときには、1週目よりも頭に残るようになっています。まずはどんどん読み進めることを意識しましょう。
もし、テキストをざっくり読んでいても、全く一切なにひとつ頭に入ってこないという人は、⑨のマンガ宅建塾をまず読むのもありです。
2.テキスト2週目+項目ごとに問題集
次に、ざっくり読んだテキストの2週目に突入します。今度はもう少し細かく勉強していきます。
どう細かく勉強するかというと、②のテキストの1項目分を読んで内容を掴んだら、すぐにその項目の問題を解きます。ここで③の問題集を使います。
1つめの項目のテキストを読んだら、その項目の問題を解く。
2つめの項目のテキストを読んだら、その項目の問題を解く。
これの繰り返しです!
この③の問題集は項目別に分かれていて、②のテキストとも連動してるので使いやすいです。問題集に復習すべきテキストのページが載っていて便利です。
例えば問題集を解いていて、答えを間違えたら記載のテキストページに戻って勉強し直す、という感じで間違えたところを潰しながら勉強を進めることができます。
この期間でコツコツ項目を潰していきましょう。
テキスト→問題集→テキスト→問題集、の繰り返しなので、くじけやすいですがココがんばりどころですね。
あとこの期間(テキスト+問題集)で、スキマ時間にはスマホアプリでの勉強するといいと思います。
朝、仕事に行く前のちょっとした時間や、通勤時の電車に乗ってる時間、仕事から帰ってご飯を食べてちょっと一息ついてる時間など、勉強するチャンスタイムです。
でもこのちょっとした時間に、「よし!ちょっとテキスト開いて勉強するか!」とはなかなかならないですよね。でもスマホアプリならやろうと思えばすぐやれるのでおすすめ!
たぶんこういうスキマ時間にスマホでTwitterやYouTubeやゲーム、やっちゃってますよね??
その内の半分でも勉強時間に変えちゃいましょう!
3.過去問+苦手な項目を復習する
ここで④の1年分ずつ過去問を解きます。
このとき、本番と同じように時間も測って、マークシートにも記入して解いていきましょう。(過去問は少なくとも2周はやりたいので、解答用紙はコピーしておくと良いかもしれませんね)
1年分の過去問を解き終わったらすぐに採点します。最初は34点以上取れるといい感じです。過去問の雰囲気になれてきたら38点以上を目指しましょう。
ただ、このタイミングでは点数に一喜一憂するのはよくないです。それよりも間違えた問題のやり直しをしっかり確実にしてください。間違った箇所の解説をよく読んで、怪しければテキストに戻って内容の復習をします。
過去問2周めは40点以上を目標にがんばってください!
4.予想模試で腕試し
いよいよ最後。本番が近づいてきました!最後は⑤⑥⑦の予想問題集をこなします。
この予想問題集はいろんな会社から出ているのですが、ここでは数をこなしましょう。
出版社によって難易度も若干違うようなので、一つだけしかやらずに「お、合格点いけるんじゃね?」と慢心するのが一番良くないですね。各社の予想問題をこなして全て合格点を取るつもりで行きましょう。
もちろん点数に一喜一憂するだけじゃなくて、間違えた問題のやり直しもしっかりと。
独学勉強を挫折せずにやり通す方法
最後に、計画通りに着実に進むためのポイントをお話します。
勉強のスケジュールを立てたのはいいけど、その後が続かない…という人いませんか?
はじめの2,3日はいいけど、ひとりで勉強してると必ず飽き(諦め?)がきます。
なかなかモチベーションが上がらないなーというときは、勉強管理アプリを使いながらモチベーションを保つといいでしょう。スタディプラスというアプリがおすすめです。
例えば「よーしここ3日間、ペース守って勉強できてる!」とか「うん!今日で20時間がんばった!」とかわかるとやる気が持続しますね。
勉強時間の可視化はとっても大事です!
それから、ちょっとしたスキマ時間にこつこつ勉強するポイントは、この短いスキマ時間もちゃんと勉強時間として記録していくことです。
前述の勉強管理アプリなら勉強する教材を選んでストップウォッチを押せば自動で記録してくれます。
この短い10分や15分を記録してくと、毎日の勉強時間が積み重なっていって、どんどん勉強している実感(=どんどんできるようになっていってる成長感)が得られます。
このサイクルがうまく回りだすと勉強することが義務じゃなく、だんだん楽しくなってきます。
「今日はちょくちょく勉強できて、もう1時間もやってる!」みたいになってくるとこっちのもの。
独学で一番大事なのはこのモチベーションを持続・維持することですね。
試験日までの孤独な戦いが続くので、試験本番までの間に「ここまでコツコツ頑張ってきたから大丈夫」という自信をつけていくのは大切です!
まとめ
ここまで読み進めてくれた方は、これから宅建試験の勉強の一歩を踏み出せそうですね。
「うーんやっぱり自分には独学じゃ無理かな…」という方は資格スクールに通うのも全然ありだと思います。もしくはオンラインの動画講座という手もありますね。
大事なのは、自分にあった方法とスケジュールでコツコツ勉強を進めていくことです。
めげずに最後までやりきってやりましょう!!応援しています!!!